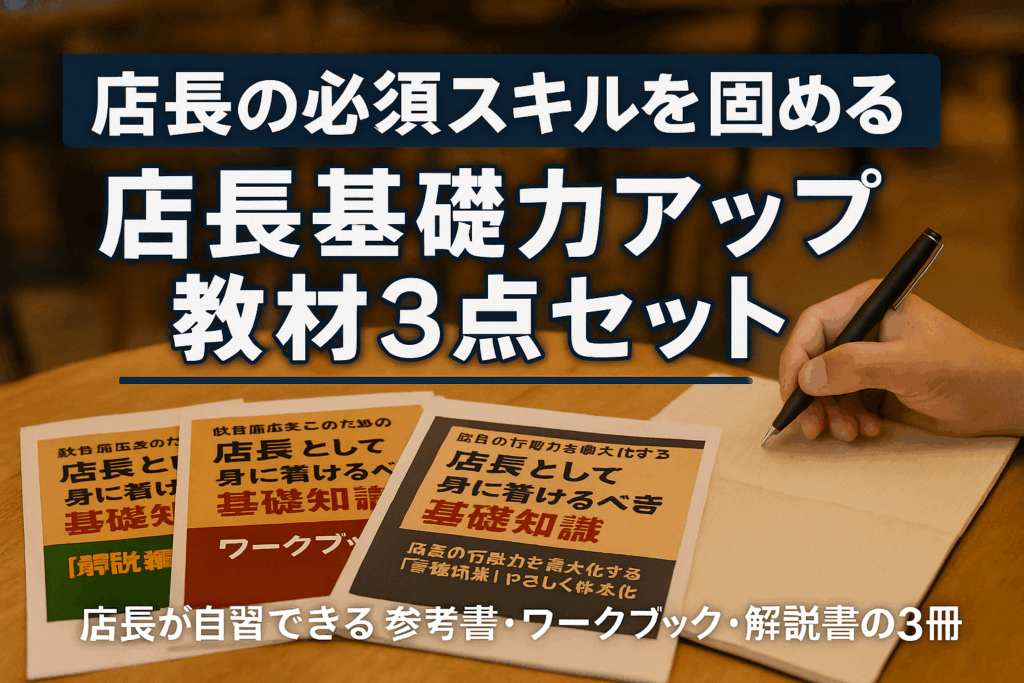店長として、最低限身に着けさせるコトとは?
10店舗未満の中小飲食店では、「店長育成をどのように進めればいいのか分からない」という声をよく耳にします。実際には、店長に求められる知識やスキルは数多くありますが、まずは土台となる“基本”を押さえることが何よりも重要です。ところが現場を見ると、その基本すら曖昧なまま店長任せになり、結果として育成や組織づくりに苦戦している企業が少なくありません。
そこで本記事では、中小飲食店が店長教育を行う際に最低限徹底してほしい9つのコトを整理しました。
売上や数値の管理、原価・人件費のコントロール、期限意識、教育やコミュニケーション、アルバイト指導まで──これらを体系的に実践することで、店長は確実に成長し、組織も安定していきます。
店長教育の仕組みを整えることは、1店舗の成果だけでなく、複数店舗を安定して成長させるために欠かせません。
※多店舗展開を成功させるための具体的なポイントはこちら →
では、10店舗未満の飲食企業、中小飲食店で店長育成を進める際に、まず教育すべき基本とは何か?どれもシンプルですが、現場ではできていないケースが非常に多いポイントです。
だからこそ、この9つを徹底することが店長を育て、組織を安定させる最短ルートになります。
それでは、順に見ていきましょう。
①飲食店の売上は顧客満足度の結果であると理解させるコト
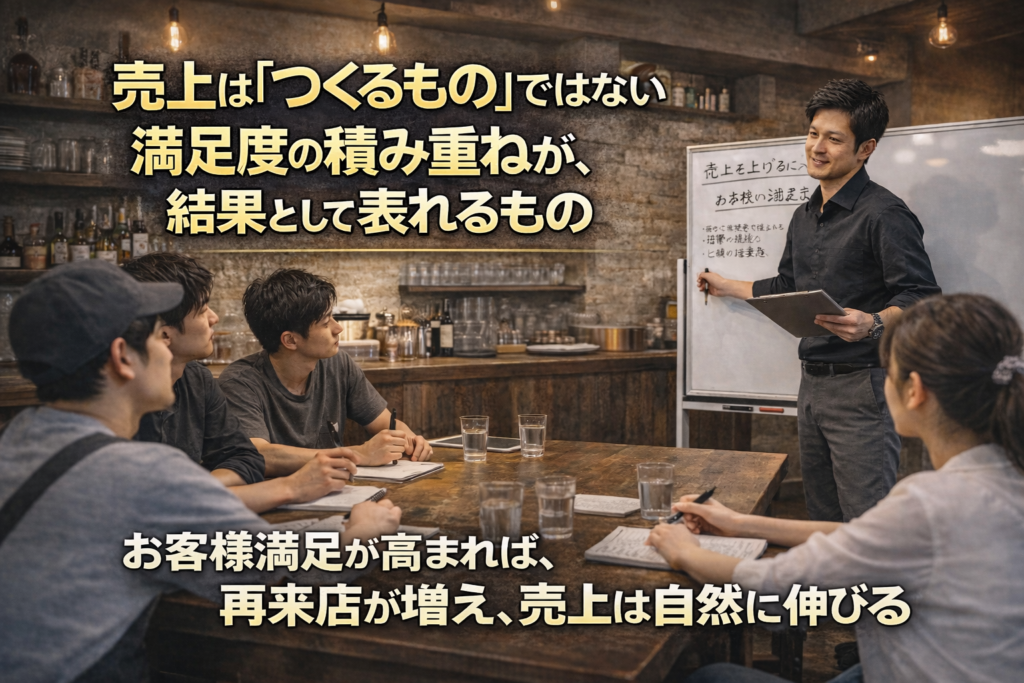
ある研修の場で「売上を上げるために何をすればいいと思う?」とスタッフに尋ねたときのこと。
返ってきた答えは,
「SNSを強化する」
「キャンペーンをやる」
といった販促策ばかりでした。誰一人として「お客様満足度が上がれば再来店につながり、その積み重ねが売上になる」という本質的な答えは出てこなかった──この事実に強い驚きを覚えたのを、今でもはっきりと記憶しています。
これは、多くの10店舗未満の飲食企業に共通する課題です。
店長やスタッフは「売上を作る方法」を体系的に学ぶ機会がほとんどなく、どうしても小手先の販促の手法しか知らいないのです。
一方、大手チェーンでは入社時に必ず QSC(Quality=商品品質、Service=接客、Cleanliness=清潔さ) の教育が行われます。そのため「店の質を高めることが売上につながる」という考え方が当たり前になり、スタッフ一人ひとりが自然と顧客満足を意識するようになります。QSCが低下すれば売上も下がる──この因果関係を理解しているのです。
だからこそ、10店舗未満の飲食企業における店長教育や研修で最初に教えるべきコトは、「売上=顧客満足度の結果である」 という基本原則です。
接客の質や料理の提供スピード、店の清潔さや雰囲気など、日々の当たり前を徹底することが顧客満足を生み、その積み重ねが数字としての売上に表れる。顧客満足度の向上こそが最大の売上対策であるという、基本的概念をしっかりと教育することをまずは重視して欲しいのです。
▼詳しくはこちら:「飲食店経営者が店長に初めに伝えるべきこと|「満足度=売上」の思考を組織に根づかせる」
②店長が押さえるべき売上管理の見方・手法を教えるコト(飲食店の計数管理の基本)

数字を知り、理解することは店長に欠かせないスキルです。
しかし、10店舗未満の飲食企業の店長の多くは「数値」に対して強い苦手意識を持っています。
その背景には、多くの研修で「損益分岐点売上高の算出方法は?」といった小難しい内容を扱いすぎてしまうことがあります。その結果、店長は「数値管理=難しいもの」という印象を持ち、数字から目を背けてしまうのです。
実際には、数値管理はもっとシンプルです。「ここを見なさい」とポイントを絞って伝えることや、「難しい計算はパソコンがしてくれる。あなたはこの数字がどう動いているかを見ればいい」と具体的に示してあげれば、多くの店長が数字に対する苦手意識を払拭できます。
そこでここでは、店長がまず押さえるべき「数字の見方と分析方法」、そして店舗経営で特に重要な FL(原価・人件費)管理 の基本について解説します。
1)飲食店店長が身につけるべき数値の見方・分析方法

売上・計数管理の目的は、数字そのものを見ることではありません。大切なのは「数字の理由を読み取り、改善に活かすこと」です。
中には「数値管理は意味がない」と言う人がいますが、それは、数値の“見方”を知らないからにほかなりません。損益計算書を一枚眺めるだけでは「売上が下がった」「原価率が高い」と感じるだけで終わり、問題点を発見することはできません。数字を活かすには“見方”を変える(違った方法で数値を管理する)ことが必要なのです。
その方法の一つが「分解すること」です。
売上が落ちているなら、客数が減ったのか客単価が下がったのか。ランチかディナーか、フリー客か宴会か、フードかドリンクか──細かく分けて見ることで、初めて原因が浮かび上がります。分解しなければ、数字はただの結果報告に終わってしまうのです。
さらに「比較する視点」も欠かせません。
原価率40%が高いと判断できるのは、業界平均が30%前後だと知っているからです。自社目標や前年同月、直近半年の推移と比べることで、変化の兆しや改善の方向性が見えてきます。
つまり、売上・計数管理で教えるべきコトは、数字を分解し、比較することで理由を見抜き、改善に活かすことです。この見方を身につければ、数字は単なる報告ではなく、現場を成長させる武器となるのです。
▼詳しくはこちら:「【飲食店向け】売上管理のやり方とコツ!売上アップに繋がる計数管理の徹底解説」
2)原価率コントロールのあり方|在庫管理と整理整頓が利益を守る
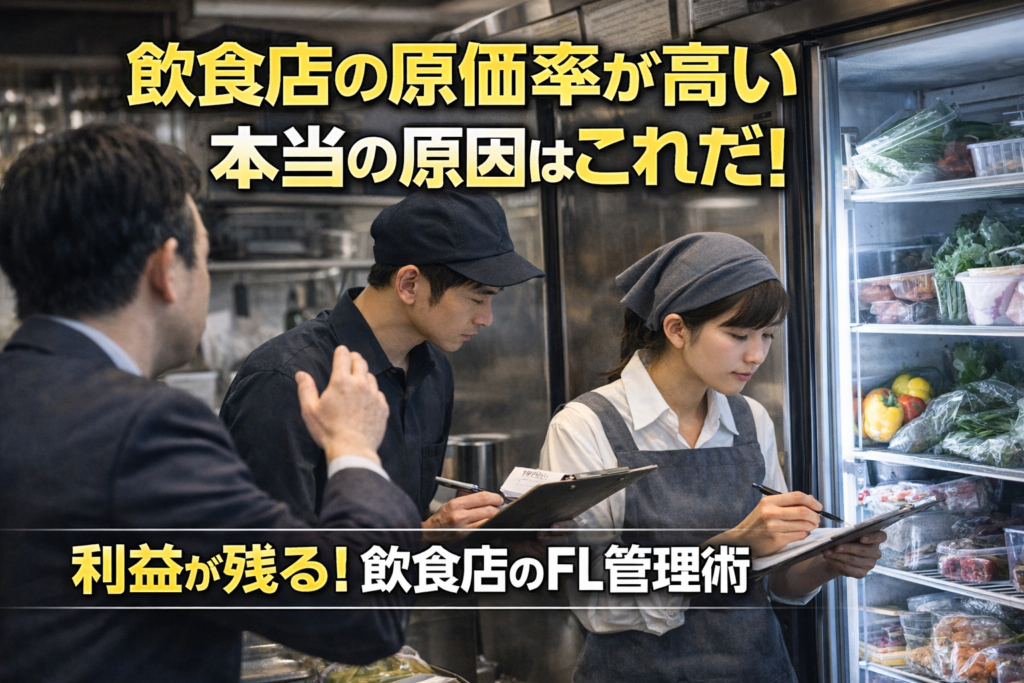
原価率のコントロールは、飲食店経営において利益を残すための要です。しかし現場では「売上が下がったから原価率が上がった」と誤解している人も少なくありません。確かに売上は間接的な影響要因にはなりますが、原価率が高くなる直接の原因は別にあります。
考えられる主な原因は次の通りです。
① ロスが増える(食材の廃棄・使い忘れ・営業中のミスなど)
② 仕入れ値が上がる(物価や市場価格の変動)
③ 原価率の高い商品がよく売れる(メニュー構成の偏り)
④ オーバーポーション(盛り付け量が安定せず多くなる)
⑤ 値引きやサービスが多い(販促やクーポン対応)
⑥ 在庫を抱えすぎている(管理不足でロスが発生)
この中でも、実際に最も大きな原因は 「在庫が多いこと」 です。
原価率の高い店舗の冷蔵庫や冷凍庫を覗くと、商品が詰め込まれ整理整頓ができていない光景がほとんど。こうした状態では「必要な食材が見つからない」「ダブル発注してしまう」といった管理ミスが頻発し、結果的にロスが膨らみ原価率が上がるのです。
だからこそ必要なのは、仕入れ率を毎日チェックすること、そして現場での 整理整頓や先入れ先出しの徹底。さらに月末には「理論原価率」と「実際原価率」の差を確認し、原因を突き止めて改善することです。
つまり原価率コントロールとは「数字を見ること」ではなく、在庫管理を徹底し、冷蔵庫や冷凍庫を整える凡事を積み重ねるコト。これを店長に根づかせることが、安定的に利益を出す店舗経営につながります。
▼詳しくはこちら:「飲食店の原価率が高い本当の原因はこれだ!」
3)人件費率コントロールのあり方|逆算式シフトで効率的に管理する
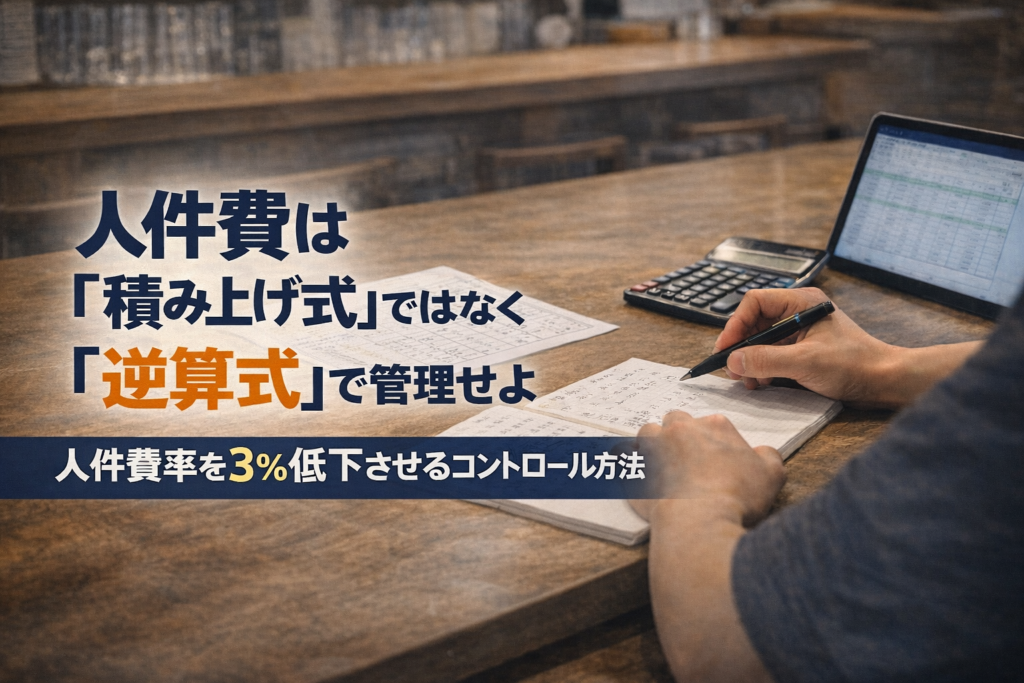
私はこれまで多くのお店を指導してきましたが、人件費管理は「結果主義」に陥っているケースが大半です。月末になって「あ〜あ、今月は人件費が35%になってしまった」と気づき、反省して終わる──このような声を何度も耳にしてきました。なぜこうした事態になるのかといえば、計画段階(シフト組み)でどれだけ人件費がかかるのかを把握していないからです。
そこで必要になるのが「逆算式」のシフト組です。
なんとなく「これぐらい人を入れれば大丈夫」と感覚で組むのではなく、まず売上予測から適正な人件費額を算出し、それを時間数に換算してシフトに落とし込む。
つまり「今月使える人件費はこれだけ=勤務時間はこれだけ」と逆算して決めるのです。
ここで大事なのが「金額ではなく時間に着目する」という視点であり、どうしても「金額」に着目してしまうのでコントロールが難しく、「時間」に着目すればアルバイトの勤務時間をシビアにコントロールできるようになるのです。
ただし注意しなければならないのは、「人件費を削ること」自体を目的化してしまうことです。
必要以上に人を減らせば、サービスの質が下がり、かえって売上ダウンを招きます。本当に考えるべきは「どうすれば効果的にオペレーションできるか」という視点です。
このページではさらに、逆算式シフト組の具体的な手法や、実際に人件費率を3%改善するための方法論を詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
▼詳しくはこちら:「飲食店の人件費率を3%低下させるコントロール方法」
③ 創業期の飲食企業こそ期限を守ることの重要性を何度も伝えるコト(店長の期限意識)

創業期の飲食企業ほど、仕事の「期限」に甘くなりがちです。だからこそ10店舗未満の会社では、期限を守る意識づけを徹底することが重要です。期限を決めずに仕事を進めると、どうしても行動のスタートが遅れ、結果の修正もできず、売上の機会を逃すことにつながります。
私自身、過去に勤めていた会社で「期限のない仕事は仕事ではない」と教え込まれました。期限があるからこそ動きが早くなり、もし結果が悪くても改善の余地が生まれるのです。逆に期限がなければ、初動が遅れて効率も落ち、経費の無駄や売上ダウンを招いてしまいます。
さらに注意すべきは、トップが期限を守らないと現場も変わらないということ。社長や幹部が率先して期限を守る姿勢を示さなければ、スタッフも責任感を持つことができません。
実際の現場業務にも期限を設定することで、スピードと質は大きく変わります。
例えば、バッシング(片付け)を「2分以内に完了させる」、ドリンク作成を「3杯を2分30秒で提供する」といった具体的な基準を設けると、動きが速くなり、回転率やサービスレベルの向上につながります。
成長している企業ほど仕事にスピード感があります。それは「期限を守る文化」が根づいているからです。だからこそ10店舗未満の企業こそ、日々の仕事に期限を設け、その重要性を繰り返し伝えていくことが、成長のために欠かせないコトなのです。
▼詳しくはこちら:「期限のない仕事は仕事じゃない!できる飲食店の店長へ導くスピード型組織の作り方」
④教育とは本学と末学をバランスよく教えるコト(飲食店店長教育の基本)

教育とは単に「店の仕事を覚えさせること」ではありません。
実際の現場を見ると、
「店の仕事はできるけれど、会社のルールを守らない」
「仲間とのコミュニケーションが取れない」
「自分勝手に行動する」
──そんなスタッフが存在し、組織がスムーズに機能しない例は少なくありません。
ここで大切なのが「末学」と「本学」の考え方です。
末学とは接客や調理といった“手法・スキル”を教えること。
一方で本学とは、その目的や背景を理解させる教育です。
単に仕事を作業として教えるのではなく、「なぜそれをやるのか」を学ばせることが欠かせません。そしてさらに本学には、「人間関係力を身につける」「人格を磨き利他の精神を持つ」「損得勘定ではなく尊徳感情を大切にする」といった意味も含まれています。
私は本学のこの部分こそが最も重要だと考えており、クライアントにも重視するように伝えています。
ただし、これを店長が直接教えるのは非常に難しいのも事実です。そこで相応するものとして会社にあるのが、「経営理念やクレド、行動指針」です。これらを活用することで、本学教育の代替となり、日常的に理念や人間性を伝えることが可能になります。
だからこそ10店舗未満の企業ほど、教育において本学と末学の両輪を意識的に教えることが必要です。特に、理念浸透を行うことこそが、本学を教えることになるので、ぜひ、お店で理念浸透に力を入れていきましょう!
▼詳しくはこちら:「“できる飲食店長”を育てる育成方法|
⑤店長に必要なコミュニケーションは関係性を深めるコト(信頼を築く会話術)

現場でよく耳にするのが「アルバイトに指示ができない」という悩みです。特にZ世代には、同年代に「上から目線」と思われるのを嫌がり、注意やお願いを言えない店長が多いのです。しかし根本的な原因は、スタッフと十分な関係性を築けていないことにあります。
関係性を築けない人に共通するのは、アルバイトやパートのことを“何も知らない”という点です。
どこの大学に通っているのか、どこに住んでいるのか、趣味は何か──基本的な情報にすら関心を持たない。結局のところ、コミュニケーション不足の最大の理由は「相手に興味がない」ことなのです。
だからこそ必要なのは、相手を知るためのコミュニケーションを強化することです。「どこに住んでるの?」「将来どうしたいの?」「休みの日は何してるの?」と友達に聞くように自然に尋ねる。そこから共通の話題や接点を見つければ、距離はぐっと縮まります。
信頼関係の上に立った指示や依頼は、相手の協力を得やすくなり、職場の雰囲気や成果も大きく変わります。店長に求められるコミュニケーションとは、単なる業務連絡ではなく、相手に興味を持ち、関係性を深めること。その積み重ねこそが、組織の力を最大限に引き出すのです。
▼詳しくはこちら:「指示できない若手が増える理由|飲食店経営者が店長に伝えたい“信頼を築く会話術”」
⑥ 毎日のアルバイト指導は、指示出しではなく目標設定で主体性を引き出すコト

アルバイト指導でありがちなのが「やっておいて」「これを片づけて」といった単なる指示出しです。しかし、それでは仕事は作業化し、アルバイトはやらされ感を覚えるだけ。結果として「つまらない仕事」となり、やりがいや成長の実感を得られません。
人が仕事に楽しさややりがいを感じるのは、「達成感」や「自分が役に立っている」という感覚を得たときです。だからこそ店長がすべきなのは、指示出しではなく“目標設定”を通じた教育です。例えば「5分でパット1枚分の食器を洗えるか挑戦してみよう」「お客様に笑顔で3回声をかけてみよう」といった具体的な目標を与えると、アルバイトは考えながら取り組むようになり、小さな達成体験を積み重ねることができます。
こうした目標設定を日々の仕事に取り入れることで、アルバイトは主体的に動き、仕事そのものが楽しい学びの場に変わっていきます。単なる労働力ではなく、自ら工夫し、成果を実感できる人材に育つのです。
つまり毎日のアルバイト指導で重要なのは、「言われたことをやる」から「自ら考えて達成する」へと意識を変えること。店長が目標設定で主体性を引き出すコトこそが、現場の活気を生み、人が育つ組織をつくる第一歩なのです。
▼詳しくはこちら:「仕事を“楽しい”に変える飲食店アルバイト教育法|指示ではなく目標で動くスタッフの育て方」
⑦ 「教える」の基本は、目的・ゴール・期限を必ず伝えるコト(飲食店アルバイト教育の基本姿勢)
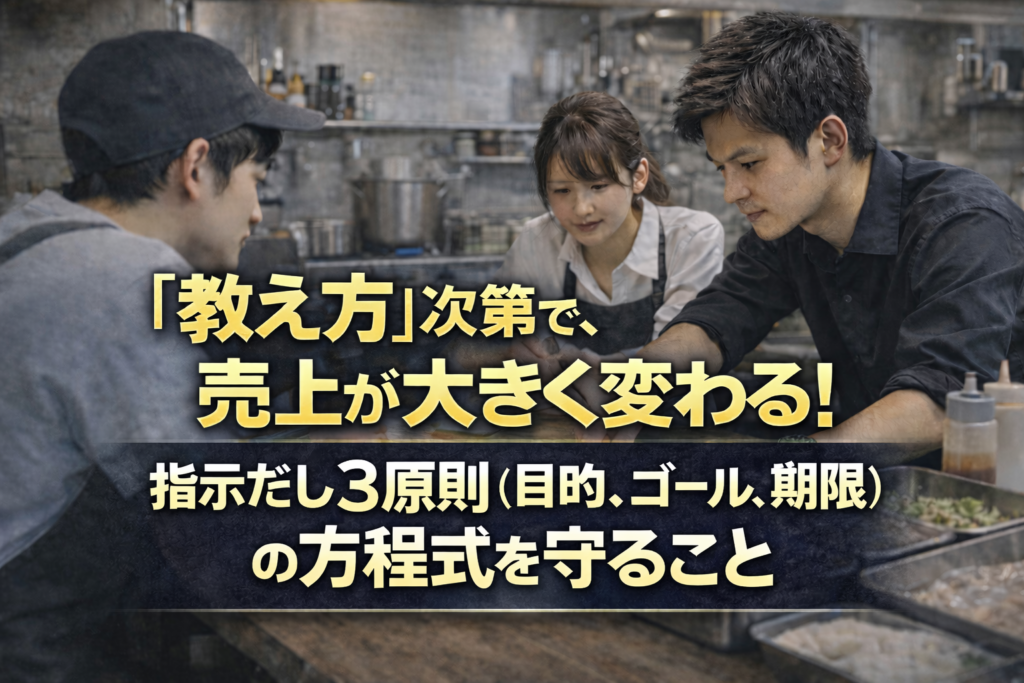
現場でよく見られるのは、「教える」と言いながら実際には単なる“やり方を伝えているだけ”というケースです。社員がアルバイトに教える際も、多くの場合は「作業」として手順を伝えるだけ。そのためアルバイトは仕事の目的や重要性を理解せず、ただ淡々とこなすようになってしまいます。
こうした状態のまま忙しい時間に入ると、間に合わせのために作業を飛ばし、「それでも問題ない」と思えばその後も抜けたまま定着してしまう。結果として「いつの間にかやらなくなる」ことにつながり、品質が崩れてしまうのです。
だからこそ大切なのが「指示出しの3原則」です。
・目的:なぜこの仕事をするのか
・ゴール:どの状態になれば完成なのか
・期限:いつまでに、どのくらいの時間で終わらせるのか
この3つを明確に伝えることで、アルバイトは単なる作業ではなく、仕事の意味を理解し、主体的に取り組めるようになります。
さらに重要なのは、教えた後のフォローです。実際にやらせてみて、できた点や改善点をフィードバックし、再度チャレンジさせる。この反復を通じて、初めて「できる」状態に到達します。
つまり店長が意識すべきコトは、「目的・ゴール・期限」を必ず伝え、形だけの作業教育を防ぐこと。それが現場の質を守り、人材を育てる基本なのです。
▼詳しくはこちら:「人が動くアルバイト教育とは?目的・ゴール・期限で設計する『できるようにさせる』飲食店のアルバイト指導法」
⑧ 店長に必須の話す・聴く・書くスキルを高めるコト(飲食店リーダーの基本力)

店長に求められる資質のひとつが、「話す」「聴く」「書く」という基本的な3つのコミュニケーションスキルです。
これらは単なる技術ではなく、組織を動かし、信頼関係を築き、学びを深めるための基盤となります。
まず「話す」スキル。
店長は自分の思いや考えをスタッフに伝える役割を担っています。伝え方が下手であれば、誤解やすれ違いを生み、組織はまとまりません。シンプルに、分かりやすく、明確に話す力が必要です。
次に「聴く」スキル。
多くの人は話すことに偏りがちですが、信頼関係を築く鍵は相手の話を受け止めることにあります。アルバイトや社員の意見や感情をしっかりと聴き、さらに質問で引き出すことが、店長に求められる姿勢です。
そして「書く」スキル。
自分の考えを文章化することで頭が整理され、新しい気づきや学びが生まれます。日報やレポートの習慣は自己成長につながり、周囲に伝える力にもなります。
この3つを磨くことは、店長自身の成長にとどまらず、組織全体を前に進める推進力となります。特にトップや幹部が率先して実践することで、現場に定着し、強い組織文化が育つのです。
▼詳しくはこちら:「飲食店の店長に必要なのは話す・聴く・書く力!|できる店長になるための3つの習慣」
⑨ アルバイト指導はダメ出しよりも達成感を感じさせるコト(仕事を楽しくする教育法)

アルバイト教育で最も大切なのは「仕事を楽しいと思ってもらうこと」です。人は楽しいと感じる仕事なら積極的に取り組み、長く働きたいと思うもの。そのための手段が「達成感を感じさせる教育」です。小さな成功体験を積ませ、本人が「できた!」と実感できれば、仕事は楽しさへと変わります。
逆に現場でありがちな「またできてないね」「どうして分からないの?」といったマイナスの言葉は、アルバイトの自信を奪い、仕事をつまらないものにしてしまいます。
そこで意識すべきは「マイナスの言葉」ではなく「プラスの言葉」で教育することです。
「今のよかったよ」「さっきより早くできたね」といった声かけは、アルバイトに達成感を与え、「次も頑張ろう」という前向きな姿勢を引き出します。
つまり、アルバイト教育の本質は、ダメ出しではなく達成感を積ませること。そしてその達成感を生み出すのは、日常の小さな場面でプラスの言葉をかけ続けることです。店長は「ダメ出しの監督」ではなく「達成感を生み出す仕掛け人」であるべきなのです。
▼詳しくはこちら:「アルバイト指導は「ダメ出し」より「達成感」|できる飲食店長を育てるための教育法」
まとめ:店長育成の9つのコトで、中小飲食店の未来が変わる!
中小飲食店における店長育成で大切なのは、複雑な理論ではなく、現場で確実に実践できる基本を徹底することです。
本記事で紹介した9つのコト──売上は顧客満足度の結果であると理解させること、数値管理や原価・人件費のコントロール、期限を守る姿勢、教育やコミュニケーション、アルバイト指導など──はいずれもシンプルですが、できていない店舗が多いポイントです。これらを体系的に実行することこそが、飲食店教育の土台であり、店長を大きく成長させ、組織を安定させる最短ルートとなります。まずはこの基本を徹底し、店長が「現場を動かせる力」を身につけることから始めましょう。
※多店舗展開を成功させる方法はこちら →
※「人を活かす多店舗化」を目指す方は、こちらの「成功メソッド12」をご覧ください→
●他社のスタッフとの交流もできる当社主催の研修であれば、「飲食店プロ店長育成研修」をご活用ください詳細は下記画像をクリックしてください↓