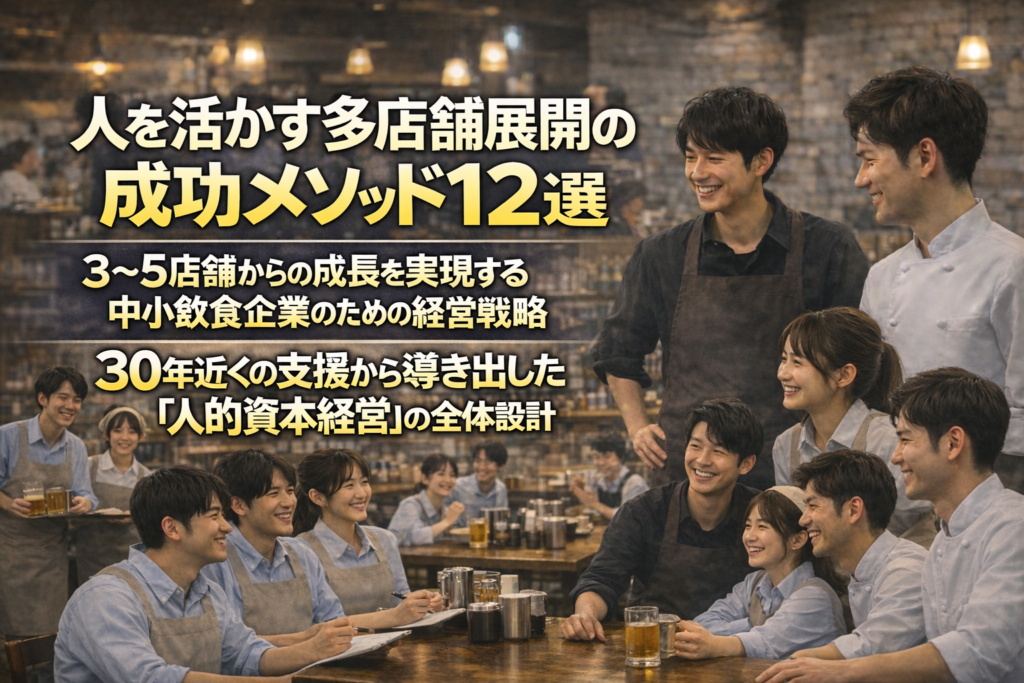あのパートさんとは一緒にシフトに入りたくない・・・
数年前の話ですが、ある会社の社員研修を実施しているときのことです。その研修のテーマは「アルバイト指導」。そこで、参加者に「アルバイト指導での悩みや課題」を発表してもらいました。
すると、ある店長がこんな発表をしました。
「当店では、あるパートAさんが『Bさんとは一緒に働きたくない』と言ってきます。なので、シフトにAさんとBさんを一緒に入れることができず、シフトを組むのに苦心しています。どうやって、仲良く仕事をさせればいいでしょうか?」
今回のテーマは「今のアルバイト指導方」に関するものでした。ですからこの質問は少しずれており、僕は半分冗談ぽく「それは自分で考えて」と返しました。
しかし、研修が終わり家に帰ったあと、ふと「あの質問に、何かいいアドバイスができなかったかな」と考えていました。そんなとき、たまたまテレビで「なでしこジャパンのキャプテン熊谷選手」の特集が流れていたのです。
共通の目標と、システムを機能させるためのコミュニケーション
当時は女子サッカーワールドカップ直前で、日本代表は12年ぶりの優勝をめざしていました。チームは新しいシステムに取り組んでおり、熊谷キャプテンは「コミュニケーションの量を増やすこと」を課題にしていたのです。
「コミュニケーション」。
飲食店でも大切で、現場ではよく耳にする言葉です。けれど私自身、「コミュニケーションを活発にする」と言われても、どうもしっくりこない部分がありました。
というのも、多くの飲食店で言われる「コミュニケーション」とは「会話をしよう」「相手と話をしよう」という意味合いが強いからです。もちろん会話自体は大事ですが、ただ会話の量を増やしたところで、それがどう店の売上につながるのかがイメージできませんでした。
また、あるご支援先のマネージャーも「A店長は、コミュニケーションをとらないことが課題です」と口にし、ここに非常に違和感を持っていました。
これも、仮に、「とりあえずコミュニケーション(会話)を増やした」としても、アルバイト・パートさんとの関係性が多少よくなるだけで、それが直接お客様の満足度を高め、売上アップにつながるとは思えなかったのです。
だからこそ私の中でも「コミュニケーションは重要だ」と頭では分かっていながら、どんなコミュニケーションをとるべきなのか、どんな目的を持って話すべきなのかが曖昧なままだったのです。
だからこそ、なでしこジャパンがしていた具体的なコミュニケーションに注目しました。
すると、彼女たちには「W杯で勝つ」という明確で強烈な共通目標があったのが一番の気づきでした。これは一見当たり前のことですが、組織にとっては決定的に重要です。
そして実際に交わされていたのは、「システムをどう機能させるか」という”目的直結”のコミュニケーションでした。
「こういうシーンでは、ここまで来てほしい」
「こんな時は、こう動いた方がいい」
「こういう場面は、自分が率先して動く」
こうしたやり取りを年齢や立場に関係なくぶつけ合い、時には「敬語禁止」というルールまで設けていました。敬語を使うとプレー中の対応が遅れたり、遠慮が生まれるからです。フラットに話し合える環境を意識的に整えていたのです。
つまり、「共通の目的」があったからこそ、勝つためのコミュニケーションが活発に行われ、チームが一体となって機能していたのです。
飲食店に必要なのは「共通の目的を達成する」ためのコミュニケーション
この姿を見て、飲食店での日常的なコミュニケーションについて改めて考えさせられました。私たちが日々行っているコミュニケーションは「相手との関係性を良くするため」の要素が強いのです。
もちろん「関係性を良くするためのコミュニケーション」も非常に重要です。特に最近は20代の店長や社員ほど、アルバイトやパートにうまく指示が出せなかったり、仕事を頼めなかったりするケースが多く見られます。その原因のひとつは「関係性をしっかり構築できていない」ことにあります。だからこそ、日頃からアルバイトやパートさんと関係性を築くためのコミュニケーションを重ねていくことは欠かせません。
そして、逆に関係性が十分に構築できていない状態で、無理に指示をしたり仕事を頼んだりするからこそ、相手から「パワハラだ」と受け取られたり、自分の指示に従ってもらえなかったりするのです。
つまり、関係性が築けていないことが、現場でのマネジメント不全を生む大きな要因になっているのです。
ただし、店を本当に良くする(売上を上げる、顧客満足度を高める、オペレーションを円滑にまわす)ためには、それだけでは足りません。
「関係性をよくする、構築するるためのコミュニケーション」だけでなく、「共通の目的を達成するためのコミュニケーション」を強化することが、飲食店には求められているのだと感じたのです。
もし、なでしこジャパンの彼女たちのコミュニケーションを飲食店に取り入れることができれば、冒頭で話した「誰々さんとは仕事はしたくない」なんてことは無くなるのではとも思いました。
きっと「誰々さんとは仕事はしたくない」という意見や考えが出て、それを許してしまうのは、店に「共通の目的」がないからだと思うのです。
もし全員が「お客様に喜んでいただくこと」という目的を共有していれば、そんな話にはならないでしょう。
しかし共通の目的があり、その達成のための会話を普段からしていれば、ただの不満ではなく「彼女は裏方の仕事をしてもらった方がいいのでは?」といった建設的な意見に変わるはずです。
つまり、普段から「仕事にフォーカスしたコミュニケーション」ではなく、「人間関係構築(関係性構築)のためのコミュニケーション」をとっているから、今回の相談のような問題が出てきたのだとつくづく感じました。
店長の役割は、「共通目的」を軸にした文化づくり
コミュニケーションをとることはすごく重要です。
しかし、コミュニケーションをとる目的がすごく大切で、それを間違えると店は全く違った方向に行ってしまうのだなと改めて思いました。
店では、皆で「共通の目的」(基本的には「お客様に喜んでいただくこと」)を明確にし、これをスタッフに徹底して伝えること。これがまず重要です。(これが理念浸透ということになります)
「この共通の目的を達成するために、日頃からスタッフ同士がコミュニケーションをとる」という文化を定着させることが、店長の役割だと言えるでしょう。
そして、よりコミュニケーションを活発にするためにも、お客様満足度につながる店舗オペレーションにおいては、各人の役割や動き、連携、フォローといった“決めごと”(いわゆるポジション制)を整えておくことが欠かせません。
この基盤がなければ、単に自分の意見を言い合うだけになってしまい、「共通の目的」を達成するためのコミュニケーションにはならないからです。
逆に、この基盤があれば、
「どうすればもっと連携やフォローがスムーズになるか」
「どうすればもっとお客様に気を配れるか」
「どうすれば案内や入れ替えをスムーズにできるか」
といったことを日頃から積極的に話し合うようになり、「共通の目的を達成するためのコミュニケーション」がより活発になるでしょう。
まとめ
結局のところ、コミュニケーションは「目的」が肝心です。
目的が曖昧なままでは、ただ会話が増えるだけで成果にはつながりません。
コミュニケーションには二つの側面があります。
①関係性を構築するためのコミュニケーション
②共通の目的を達成するためのコミュニケーション
どちらも欠かせませんが、目的を意識して取り組むことで、コミュニケーションの内容もやり方も変わってきます。
店のオペレーションを良くすること、そして、スタッフ同士のイザコザをできるだけ減らすためには、「関係性を構築するためのコミュニケーション」だけでは足りません。
もう一つ、「共通の目的を達成するためのコミュニケーション」を日常的に強化することが必要です。これを強化することで、それぞれの課題を解決することにつながるでしょう。
皆さんのお店ではどうでしょうか?
「共通の目的」をスタッフ全員で共有できていますか?
そして、その目的を達成するためのコミュニケーションが、日常の現場でしっかりと行われているでしょうか?