
「売れる」「売れ続ける」飲食店には必ず”理由”がある!
競争が激しい飲食業界。
原材料の価格高騰、人手不足、働き方改革など、経営者にとって“マイナス要素”が多いこの時代。
それでもなお──
「売れている」また「売れ続けている」飲食店があるのは事実です。
なぜでしょうか?
私は、この業界で30年近くコンサルタントとして活動してきました。
その中で強く感じるのは、「売れ続ける店」には必ず共通点があるということ。
今回は、その共通点を7つに整理して紹介します。
それぞれのポイントについて、詳しい解説ページへのリンクも付けていますので、気になる項目からぜひ読み進めてみてください。
① コンセプトに基づいた店づくりこそ、飲食店が売れ続ける理由

「売れ続ける飲食店」には、必ずといっていいほど揺るがないコンセプトがあります。
どんなに時代が移り変わろうとも、「この店は何を提供するのか」「お客様にどんな価値を届けるのか」という軸がぶれていません。
逆にコンセプトが曖昧な店は、メニューやサービスが場当たり的になり、お客様の頭に残らなくなります。結果として、価格競争に巻き込まれたり、一時的なブームが去った途端に失速してしまうことが多いのです。
売れ続ける飲食店は、コンセプトを単なる“言葉”にとどめず、商品、サービス、接客、空間、広告宣伝に至るまで一貫させている点が大きな特徴。だからこそ「この店だから行きたい」と思ってもらえるのです。
▼さらに詳しくはこちら
「生き残る飲食店の共通点|コンセプトを本当に理解して行動できているかどうか」
そこで、コンセプトを構築していくにあたって、特に下記の4つが今の時代とても重要だと感じています。それぞれの考え方を紹介します。
1)飲食店のアイデンティティを強めるペルソナ戦略
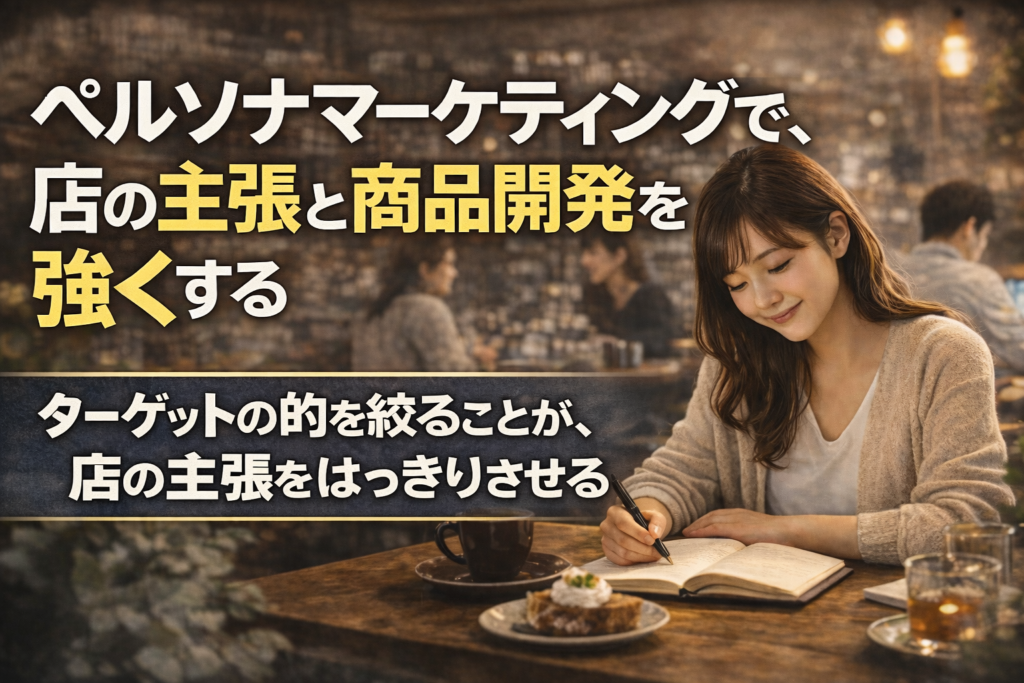
今は「誰でもいいから来てほしい」では生き残れない時代です。
業態の多様化やSNSの普及で、お客様のニーズは細分化し、昔のように「20代女性」といった大まかなターゲット設定では共感されにくくなっています。
たとえば「20代女性」と一括りにしても、学生もいれば主婦もいて、好みやライフスタイルは全く異なります。その結果、“ありきたりな店”と見られてしまう危険があるのです。
そこで重要になるのが「ペルソナマーケティング」。
ペルソナとは、理想のお客様像を年齢・職業・ライフスタイルなどで具体的に描いた人物モデルのこと。これを設定することで店の主張がクリアになり、他店との差別化も明確になります。さらに「この店は自分のためだ」と感じてもらえる強みにつながるのです。
スタッフへの共有や商品開発・接客の一貫性にも効果的な、このペルソナの作り方については──
▼さらに詳しくはこちら
「ぼんやりしたターゲットは卒業!飲食店のアイデンティティを強めるペルソナ戦略」
2)利用シーンと価格が一致する店は生き残る仕組みを持っている

飲食店にとって「価格設定」は単なる金額の問題ではなく、“お客様がどんな時に使いたいか”という利用シーンと深く結びついています。
例えば、仕事帰りに気軽に立ち寄るお店なのか、記念日や特別な日に選ばれるお店なのか。その位置づけが曖昧なままでは、お客様の期待とのギャップが生まれ、リピートにはつながりません。
多くの店が「安ければお得だろう」「高級感を出せば特別に見えるだろう」と安易に価格を設定しがちですが、それだけでは長続きしません。お客様がその価格に納得するのは、「このシーンで利用するなら、この金額がちょうどいい」と感じられたときだけなのです。
「売れ続ける飲食店」は、この“利用シーンと価格の一致”を徹底的に意識しています。客層や来店目的を整理し、そのシーンごとにふさわしい商品構成やサービスを整えることで、価格が自然に受け入れられる仕組みを作っているのです。結果として「この店は安心して使える」「また来たい」と思われ、リピーターが生まれ続けていきます。
では、この“シーンと価格の一致”をどのように仕組みに落とし込めばよいのか──
▼さらに詳しくはこちら
「飲食店経営の根幹|利用シーンと価格が一致する店は生き残る仕組みを持っている」
3)飲食店の差別化は体験から|コーヒーの例に学ぶ、顧客に伝わるコンセプトの作り方

飲食店で「差別化」と聞くと、多くの経営者は“味”や“商品力”を思い浮かべます。もちろんそれも大切ですが、それだけでは他店との差が分かりにくくなっているのが現実です。今の時代に本当に効く差別化は、お客様が店で得る“体験”なのです。
例えばコーヒーを例に考えてみましょう。
同じコーヒーでも、コンビニで100円で買える一杯と、カフェで時間をかけて丁寧に淹れてもらう一杯とでは、体験の価値がまったく違います。そこには「味」だけでなく、提供の仕方、空間の雰囲気、スタッフの接客など、複数の要素が積み重なって“特別な体験”を作り出しています。
「売れ続ける店」は、この体験設計をとても大事にしています。味や価格を超えて「このお店に来たい」と思わせるのは、そこでしか味わえない体験だからです。逆に、体験が希薄でどこにでもある内容になってしまうと、お客様の記憶に残らず、再来店の理由も生まれません。
では、どうすれば自分の店の体験を魅力的に設計し、顧客に伝わるコンセプトへと昇華できるのか──
▼さらに詳しくはこちら
「飲食店の差別化は体験から|コーヒーの例に学ぶ、顧客に伝わるコンセプトの作り方」
4)飲食店の売上アップの根本は品揃えにあり
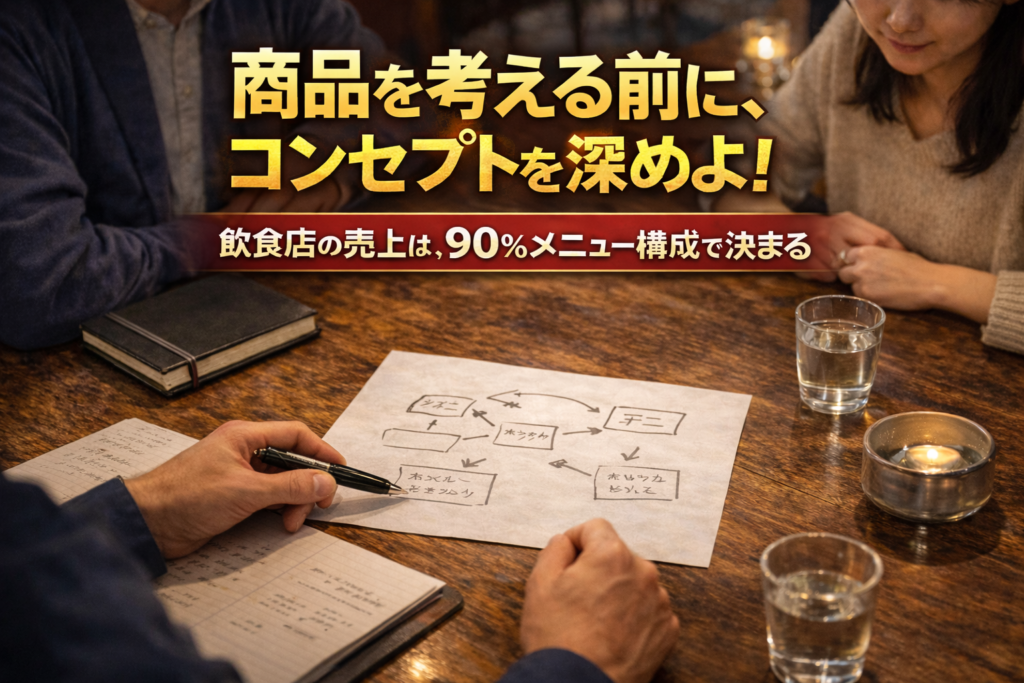
「コンセプトを深めなければ売上は上がらない」という店長や社長の反応には、「その通り…でも、今はどんな商品を置けばいいかを知りたい!」という本音も透けます。
しかし、実際に売上を決めるのは、「どんな商品を構成するか」なのです。なぜなら、飲食店にとって「何を提供するか」は、存在価値の中核だからです。
これは、誰が来店し、どんな目的か、そして立地や消費スタイルによっても、品揃えは変わることを意味しています。だからこそ、「ターゲット」「利用動機」「立地状況」「消費形態」の4要素がリンクした、一貫性あるメニュー構成が売れる店には不可欠です。
さらに重要なのは、他店にはない“主張”や“強み”が明確に伝わるかどうかです。お客様から見て「この店って、同じタイプの店と何が違うの?」と思わせないためにも、差別化となる体験や価値提供が必要です。
私自身もお店の方と対話を重ねる中で、「理想の顧客像」「利用されたいシーン」「どんな体験をしてほしいのか」といった話を通じて、店の“軸”を深めていきます。そうして見えてくるのが、「楽しみの提供」「驚き」のようなキーワードであり、それらがメニュー・接客・空間を貫く原動力になるのです。
こうしてコンセプトが明確になると、「どんな商品を、どれくらいの価格帯で出せばいいか」が自然と浮かび上がり、商品構成にも一貫性が生まれます。逆にコンセプトが浅いまま“商品だけ増やす”ことを続けると、店の「軸」がブレてしまい、お客様にも響かなくなってしまうのです。
では、このような一貫性のあるメニュー構成をどのように設計し、売上に結びつけていけばいいのか──具体的な手順はここで詳しく解説しています。
▼さらに詳しくはこちら
「飲食店の売上アップの根本は品揃えにあり|ターゲット・動機・立地を反映した理論的メニュー設計」
② 潜在ニーズに応えることが、飲食店が売れ続ける理由になる

飲食店では「お客様が喜ぶものを出そう」と考え、どうしても“顕在ニーズ”に偏りがちです。
しかし、それだけでは「どこにでもある普通の店」になり、選ばれ続ける理由にはなりません。
実際に、私が以前ご支援していた会社での出来事です。
宴会メニューを考えているときに、私がこう投げかけました。
「これ、いつも同じメニューやん。それに、唐揚げが宴会メニューに入っていて、お客様は本当に喜ぶと思う?」
すると担当者はこう答えました。
「いや、お客様は喜んで食べています。だから唐揚げを出す方がいいと思います」
確かに、日本人は唐揚げが大好きですし、数年前には唐揚げ専門店の出店ラッシュもありました。
でも実際には「唐揚げだから喜んでいる」わけではなく、たまたま出てきたから食べているに過ぎないのです。
もしそのお店独自のアレンジを加えた料理や、普段なかなか食べられない一品を出せば、お客様はもっと驚き、もっと喜んでくれるはずです。
つまり、「お客様が声に出して求めているもの」だけに応えるのではなく、「まだ気づいていない期待=潜在ニーズ」に踏み込むことで、飽きさせずに何度も足を運んでもらえる店になるのです。
では、潜在ニーズをどう読み取り、商品やサービスに反映させていけばいいのか──
▼さらに詳しくはこちら
「普通でなくなる」飲食店の秘訣|唐揚げ以外の驚きを届ける潜在ニーズの掘り方」
③ 社長や幹部が“厳しいお客様”になることも、売れ続ける理由のひとつ

現場のスタッフに「お客様目線で考えろ」と言っても、実際には難しいものです。
なぜなら、普段現場に入っている人ほど「これは業務上どうしても必要だから…」「言ってることは分かるけど実際にはムリ」などと、どうしても自分たちの都合を優先してしまうからです。
この視点のズレこそが、お客様満足を下げる原因になります。
本当は「もっとこうしてほしい」と思われているのに、現場からは「これくらいで十分」と判断されてしまう。結果として、気づかぬうちにお客様の期待とのギャップが広がっていくのです。
だからこそ必要なのが、社長や幹部が“最も厳しいお客様”になることです。
現場を客観的にチェックし、「これでお客様は本当に喜んでいるか?」と自ら問いかけ続ける。そして一度決めたやり方を「もう大丈夫」と思わず、常に“上書き”していく姿勢が重要です。
そうして積み重ねられた小さな改善の連続こそが、「この店はやっぱり安心できる」「何度でも来たい」と思わせる理由になります。
では、具体的にどんな視点で“上書き”を続けていけばよいのか──
▼さらに詳しくはこちら
「経営者こそが本物になれ!自ら“厳しいお客様”として現場に接する飲食店成長術」
④ お客様“不”満足を解消し続けることが、売れ続ける理由をつくる

飲食店の来店には、大きく2つの形があります:
衝動来店型 と 目的来店型。これらでは重視すべき売上対策が異なるのです。
衝動来店型 :衝動的に店を利用するタイプのお店
・有効な施策:立地の良さ(通り沿いなど目につく場所)+早い提供・低価格
・商品力より、スピードとコストパフォーマンスが重視されます。
目的来店型 :「わざわざ」利用するタイプのお店
・有効な施策:リピーター獲得の設計
・お客様の再来店を促すには、満足度を徹底的に高めることが成功の鍵です。
特に目的来店型のお店では、顧客が抱える「小さな不満=“不”満足」にこそ着目する必要があります。
店の問題点を「設備が古い」や「人手不足」などの内部要因だけだと捉えるのではなく、「お客様にとっての不満足」として捉え直すことが重要。それらを毎月具体的に抽出し、優先的に改善していく姿勢こそが、売れる店に共通する“地に足のついた戦略”なのです。
こうして不満足を一つずつ確実に取り除き続けることで、販促費をかけずとも、スタッフ全員が同じ方向に向かって動きやすくなり、結果として売上は着実に伸びていきます。これはまさに、「売れ続ける店」になる最大のコツといえるでしょう。
では実際に、目的来店型の店舗が“お客様の不満足”をどう特定し、改善していくのか──
▼さらに詳しくはこちら
「飲食店が売れ続ける秘訣|「お客様不満足」を毎月解消する現場の仕組み」
⑤ 流行りの業態に手を出さない!

飲食業界では、新しい業態やブームが次々と登場します。しかし、流行に乗ることが必ずしも成功につながるわけではありません。実際、模倣しやすいがゆえに「一時注目されても、すぐに飽和して消えていく」というケースが多いのです。これはまさに「コモディティ化」、つまり“ありふれた存在”になる典型的なパターンです。
歴史を振り返ると、もつ鍋やジンギスカン、タピオカ、食パン、さらにはから揚げ専門店など、「一時は流行ったけれどすぐ消えた業態」もたくさんあります。一方で、生き残ったものもある。結局なんと言っても、「長く続く業態」は“自分たちの愛せる、磨き続けられる業態”なのだと感じます。
実例として、2008年にご支援していた地方の焼き鳥チェーンがありました。不景気やリーマンショックのあおりで多くの飲食店が苦戦する中、この会社は「景気に左右されない人気業態」であったため、売上を伸ばし続け、好調を保っていました。こうした業態の力は、経営の耐久性を生む強さと言えます。
つまり、会社を永く存続させたい、店をずっと愛される場所にしたいと考えるならば、流行りに手を出すより、「自分が愛せる業態」を見つけて、毎日少しずつ磨きあげていくことが何より大切です。そうした姿勢こそが、“売れ続ける店”になるための根本的な戦略です。
では、流行りに左右されず、自店の価値を深めていくためには、具体的にどんな考え方や行動が必要なのか──
▼さらに詳しくはこちら
「飲食業界の落とし穴|流行追随では終わらない、長く愛される業態戦略とは」
⑥ 「飲食を楽しませる」ことができる店に人は集まる!

今の飲食業界で一番の悩みと言えば「人不足」。
その解決方法として、タッチパネル導入やスマホ注文、さらには配膳ロボットといった“IT活用”が進んでいます。確かに合理的ですが、外食の醍醐味は“楽しみ”にあります。
私自身、外食に求めるのは以下のような体験です:
・スタッフから「今日のおすすめ」を案内してもらいたい
・好奇心をくすぐる説明や一言がほしい
・空いたお皿は自然に下げてほしいし、気づかいある声かけも嬉しい
こうした体験が外食の価値です。もしこれができないなら、家でデリバリーで済ませたほうがいい、と感じてしまうかもしれません。逆に、こうした体験があるからこそ「外に出てお金を使ってでも行きたい」と思えるのです。
現代は多様性の時代。「食べられればいい」というお客さまも当然いますが、やはり「食を楽しみたい」と思って来店される方もたくさんいるのです。飲食店の役割は、単に“飲食を提供する”だけでは足りません。
むしろこの「楽しませる」力こそが、人で埋められない“人にしかできない価値”です。機械やロボット化には代替できない、人の温かさや会話、気づきによって生まれる体験こそが、飲食店の強みになります。
たとえばスターバックス。今の時代でも「人手不足」という話をあまり聞かないのは、「お客様を楽しませること」を徹底しているからではないかと思います。そうした店には、そもそも「ここで働きたい」と思える人も集まるんですね。
次は、そんな「楽しませる力」をどう具体的に設計していくか──
▼さらに詳しくはこちら
「飲食店が人に選ばれる理由|楽しませる接客こそ“人”だから実現できる工夫」
⑦ お客様の頭の中で「検索第1位」になっている!

いまや情報検索はスマホで簡単にできる時代。
でも、飲食店にとって本当に大事なのは「Googleでの順位」よりも、お客様の頭の中で“真っ先に思い出される店”になることです。
「今日、イタリアンに行きたいな」と思ったとき、最初に浮かぶお店がある。
「久しぶりにあの店の味が食べたい」と自然に思い出してもらえる。
この“頭の中の検索1位”こそが、「売れ続ける店」に共通する強さです。
では、そのためにはどうすればよいのか?
単に広告やクーポンを打つだけでは足りません。お客様に「この店といえば◯◯」と強く印象づけられるような、体験・価値・ストーリーを一貫して届け続けることが欠かせないのです。
ブランディングとはロゴやデザインだけの話ではなく、お客様の記憶に“特別な存在”として残る仕組みをつくること。
これができているお店は、多少の競合や値上げがあっても揺るがず、長期的に選ばれ続けます。
では実際に「頭の中の検索1位」になるために、どんなブランディングが必要なのか──
▼さらに詳しくはこちら
「ブランドは自ら名乗らず“思い出される”飲食店になること|外側と内側の両輪で作る飲食店経営のブランド戦略」
まとめ:「売れ続ける飲食店」は“特別な魔法”ではなく、日々の積み重ねから
今回紹介した7つのポイントは、どれも特別なテクニックや一発逆転の方法ではありません。共通しているのは、お客様にとっての価値を徹底して考え、日々の営業の中で小さな改善を積み重ねているということです。
一方で、売れ続けないお店は「今はこれで十分」と現状に安住してしまいがちです。結果としてお客様の“不”満足に気づけず、いつの間にか選ばれなくなっていきます。
逆に売れ続けるお店は、コンセプトを大切にしながら商品や体験を磨き込み、潜在ニーズや不満足を解消し続けています。そして流行に流されず、飲食を楽しませる工夫をしながら「頭の中の検索第1位」を勝ち取っているのです。
つまり、”売れる”“売れ続ける秘訣”とは、派手な仕掛けや流行に頼ることではなく、お客様に真剣に向き合い、やるべきことを継続する姿勢そのもの。
この7つの視点をぜひお店に照らし合わせ、明日から一つでも実践してみてください。

