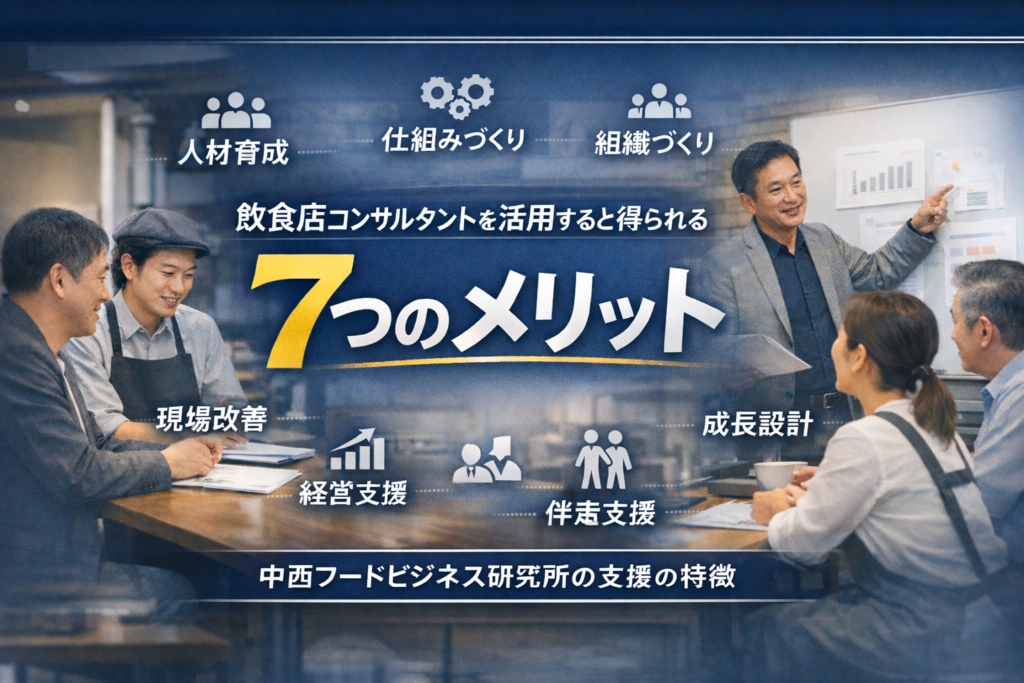
飲食店経営コンサルタントとは?よくある誤解と本当の役割
「飲食店経営コンサルタント」という仕事。
基本的には、飲食店の経営改善や人材育成、仕組みづくりを専門に支援する存在です。
こうした支援全体をまとめて“飲食店経営コンサルティング”と呼びます。
しかしながら、人によっては「胡散臭い」「自分の店には必要ない」と思う方もいるかもしれません。
ただ、実際には──
・経営者の思いやビジョンを引き出して整理してくれる
・成長スピードを加速させるノウハウを持っている
・社員教育や仕組みづくりを客観的に支援してくれる
こうした役割を果たせるのが、飲食店コンサルタントです。
つまり、上手く活用すれば“単なる費用”ではなく“未来への投資”になります。
特に飲食店の場合、業態やステージによって直面する課題が大きく異なります。個人店と多店舗展開を進める企業では、求められる仕組みも教育の方法も全く違います。だからこそ、飲食店の現場に精通したコンサルタントをどう活用するかが、経営の分かれ道になるのです。
ここでは「飲食店コンサルタントを活用すべき7つの理由」として、一般的なメリットに加え、私(中西フードビジネス研究所)が実際に行っている支援の特徴や強みも交えてご紹介します。
①経営者の思いを引き出し、理念や方針に形にしてくれる【飲食店経営コンサルタントの一番の役割】
コンサルタントを活用すると得られること
飲食店コンサルタントを活用すると、経営者が頭の中に持っている考えやビジョンを整理し、それを具体的な言葉や仕組みに落とし込んでくれます。
経営者は日々の判断や業務に追われ、「本当はこうしたい」という思いがあっても、なかなか言語化する時間がありません。結果として、現場任せになってしまうケースも多いのです。
外部のコンサルタントが入ると、第三者の立場から質問を投げかけ、経営者の言葉を整理します。これによって頭の中のイメージが明確になり、経営理念や経営方針として社員に伝わる形に整えられるのです。経営者にとって、思いが「言葉になり」「仕組みになる」ことは、大きな一歩となります。
他社コンサルでありがちなこと
ただ実際には、多くのコンサルタントは「ヒアリング」こそ行うものの、そこで止まってしまう場合が少なくありません。
ありがちなのは──
・既存のテンプレートやフレームワークに当てはめて提案するだけ
・販促やキャンペーンなど、売上アップの打ち手を中心に提案するだけ
これでは経営者の本当の思いを形にし、会社全体の軸にすることはできません。
私の支援スタイルではここに踏み込みます
私が必ず行うのは、経営者の思いを徹底的に引き出し、それを「人を活かす飲食店経営」という軸に沿って、仕組みや戦略に変換することです。
「どんな会社にしたいか」「どんなスタッフを育てたいか」「お客様からどう思われたいか」といった価値観を聞き出し、経営の根幹として整理するために、とにかく経営者からのヒアリング(聴く時間)に多くの時間を使います。これが、私のコンサルティングの一番の特徴です。聴くことによって、経営者の本位をくみ取るからこそ、経営者の”本当の思い”を実現できる支援ができるのだと思います。
さらに、ときには経営者に代わって社員へ直接伝えることもあります。外部の立場だからこそ言える厳しい言葉が、社内に適度な緊張感を生み出し、行動を後押しするのです。
つまり、単なる「聞き取り」や「既成の型への当てはめ」で終わらせず、経営者の思いを仕組みに落とし込み、現場で動かすところまで徹底する。ここが私のコンサルティングの大きな特徴です。
※経営者の思いをトコトン聴くことことから始める、「顧問型(伴走型)コンサルティング」の案内はこちら>>>

②会社の成長スピードを上げられる
コンサルタントを活用すると得られること
飲食店経営を進めると、必ず「成長の壁」にぶつかります。
例えば──
・2店舗から3店舗に拡大したときに現場が混乱する
・店長や社員の教育が追いつかず、品質にバラつきが出る
・採用が難しくなり、人材不足が慢性化する
こうした課題は、経営者にとって“初めて”の経験です。独力で乗り越えることもできますが、解決までに時間もコストもかかってしまいます。
そこでコンサルタントを活用すれば、すでに数多くの事例を見てきた経験値をもとに「最短ルートの解決策」を得ることができます。結果として、無駄な試行錯誤を避け、会社の成長スピードを大幅に高めることができるのです。
他社コンサルでありがちなこと
ただし、多くのコンサルタントは「売上アップの打ち手」や「既存の成功事例の横展開」に偏りがちです。
・キャンペーンや販促策を提案して一時的に売上を伸ばす
・既存のテンプレートやフレームワークに当てはめるだけ
確かに短期的には数字が伸びますが、土台となる仕組みや人材の育成が追いついていなければ、再び同じ壁にぶつかってしまいます。
私の支援スタイルではここに踏み込みます
私が30年近く支援してきたのは、特に10店舗未満の飲食企業です。
この規模の会社は「人材不足」「仕組み不足」「経営者への依存度が高い」といった課題を抱えやすく、だからこそ 「人を活かす飲食店経営」 が成長のカギになります。
私のコンサルティングでは、
・基盤づくり:理念や方針を整理し、会社としての軸を固める
・仕組みづくり:店舗拡大に耐えられる最低限の仕組みを整える
・教育づくり:店長やスタッフが自走できるように成長を支援する
という「人を活かす経営の土台づくり」に徹底的に取り組みます。
マニュアルを押しつけるのではなく、人の成長が会社の成長につながるように設計するのが私のスタイルです。だからこそ、一時的な売上アップではなく、人と組織が一緒に成長し続けるための仕組みを整え、成長スピードを加速させていくのです。

③社員教育を通じて組織を成長させられる【飲食店経営コンサルタントによる育成支援】
コンサルタントを活用すると得られること
飲食店の成長に欠かせないのが「社員教育」です。
特に会社としての歴史が浅い段階では、
・「何をどう教えればいいのか分からない」
・「教育の仕組みが整っていない」
・「現場任せのOJTになっている」
といった課題を抱えがちです。
外部のコンサルタントが入ることで、自社にはない教育ノウハウや仕組みを取り入れることができ、社員の成長スピードを早めることができます。
他社コンサルでありがちなこと
ただし、多くのコンサルタントは「既成の研修プログラム」をそのまま提供するだけだったり、「教育」と言いつつ販促や接客スキルだけに偏った研修を行うことも少なくありません。
これでは一時的なスキルアップにはつながっても、会社の課題解決や組織の成長には直結しません。
「教育が目的化してしまう」ことも多く、本来のゴールである「人を活かす組織づくり」からズレてしまうのです。
私の支援スタイルではここに踏み込みます
私が大切にしているのは、教育を“会社の課題解決のための手段”と位置づけることです。30年近く10店舗未満の飲食企業を支援してきた経験から、同じ規模でも課題は一社ごとに違います。
だから私は必ず、
・幹部や店長、スタッフにヒアリングを実施し、現状を客観的に分析する
・実際に店舗を訪問し、オペレーションや接客の実態を把握する
・その上で「今この会社に必要な教育」を設計する
という流れを徹底しています。
さらに「教育=研修で教えて終わり」ではなく、仕組みに落とし込むところまで支援するのが特徴です。例えば、教育内容を評価制度や日々のチェックリストと連動させたり、店長が部下を育てられる仕組みに置き換えたりすることで、教育が“現場で生きる仕組み”になります。
つまり、私の教育支援は「単なる研修」ではなく、人の成長を会社の成長につなげるための仕組み化なのです。これこそが「人を活かす飲食店経営」を実現するための教育支援であり、私が最も得意とする領域です。
※こちらのページに、当社の「社員教育・研修」に関する考え、具体的プログラムを案内しています>>>

④客観的な視点でのアドバイスがもらえる
コンサルタントを活用すると得られること
経営者が自分の会社を見ていると、どうしても「自分の思い」や「現場の慣習」に引っ張られてしまいます。気づかないうちに方向がずれていたり、問題が見えなくなってしまうことも少なくありません。
外部のコンサルタントは第三者の立場から関わるため、経営者が見落としがちなポイントを客観的に指摘できる存在です。ときには「そのやり方は本当に正しいですか?」と立ち止まらせてくれることで、大きな間違いを未然に防ぎ、経営の軸を修正するきっかけを与えてくれます。
他社コンサルでありがちなこと
ただし、多くのコンサルタントは「一般論」や「他社事例」をベースに指摘することが多いのが現実です。
・業界の成功モデルに当てはめて判断する
・数値や制度だけを基準にアドバイスする
これでは確かに“正しい答え”のように聞こえますが、その会社の文化や理念に合わないケースも多々あります。結果として「数字は整ったけど、人がついてこない」という事態になりかねません。
私の支援スタイルではここに踏み込みます
私は、支援の初期段階で「経営方針書」を必ず作成します。
経営理念・ビジョン・バリュー・店舗のコンセプト──会社の“軸”をしっかり整理したうえで、すべてのアドバイスや教育を進めていきます。
だからこそ、経営者が方向を誤りそうになったときにも「その判断は軸に合っていますか?」と立ち返ることができます。単なる「数値管理の正解」ではなく、人を活かす飲食店経営という土台に基づいたアドバイスを行うのが、私のスタイルです。
また、私は経営者と本気で向き合うので、ときには激しく意見がぶつかることもあります。でもそれは、お互いが本気で「会社と人を成長させたい」と思っている証拠。だからこそ私も遠慮せずに伝え、経営者の思いを尊重しながら“軸に沿った修正”を加えていきます。
つまり、私のコンサルティングは「ただの客観視」ではなく、経営者の思いを支えながらも、会社全体を“軸”に立ち返らせる存在であることを大切にしています。

⑤仕組みを構築できる【飲食店経営コンサルタントの強み】
コンサルタントを活用すると得られること
会社が3店舗、5店舗と拡大していくと、必ず必要になるのが「仕組み」です。
・店舗ごとのやり方がバラバラ
・店長任せのマネジメント
・経営者がすべてを抱え込んで疲弊
こうした状況を解消するためには、業務フローや教育体制、評価制度などの仕組みが不可欠です。コンサルタントが関わることで、外部の経験やノウハウを取り入れ、自社に合った仕組みを効率よく構築することが可能になります。
他社コンサルでありがちなこと
ただし、多くのコンサルタントは「既存のテンプレート」をそのまま持ち込み、当てはめる形で仕組みを導入することが少なくありません。
また、経営者の相談に対して「マネージャーを採用しましょう」と安易に提案するケースもあります。
しかし、例えば月給40万〜50万円クラスの人材を雇ったとしても、会社にフィットするとは限らないのが現実です。結果として、高い人件費を払い続けても期待通りの成果が出ず、やがて辞めてしまう…そんな事例を多く見てきました。
私の支援スタイルではここに踏み込みます
私が行う支援(飲食店経営コンサルティング)は、「人を活かす飲食店経営」を実現するための仕組みづくりです。仕組みは「人を縛るもの」ではなく、「人が動きやすくなる土台」であるべきだと考えています。
そのために取り組むのは、
・基盤にある理念を反映した仕組み
・現場のスタッフが理解・実行できるシンプルな仕組み
・教育と連動して機能する仕組み
です。
さらに、私の顧問料は月20万〜30万円程度。
マネージャーをひとり雇うよりも低コストで、仕組みづくりから教育、現場浸透までトータルに支援します。つまり「人をひとり雇う」のではなく、会社全体の成長を支える仕組みを整える投資になるのです。
結果として、既存の人材が成長しながら動ける環境が整い、人を活かす仕組みが会社の成長を長期的に支えていきます。
※当社のコンサルティングの支援内容、費用について詳しくはこちら>>>>

⑥経営者の相談相手ができる
コンサルタントを活用すると得られること
経営者は常に孤独な存在です。
最終的な判断はすべて経営者自身が行わなければならず、社内には同じ目線で相談できる相手がほとんどいません。だからこそ、外部のコンサルタントが経営者の相談相手になることは、大きな安心感につながります。
ときには事業の方向性を一緒に考えたり、人事や教育の悩みを聞いたりすることで、経営者の頭が整理され、次の一手を冷静に決断できるようになります。
他社コンサルでありがちなこと
ただし、多くのコンサルタントは「アドバイスを与えること」が中心になりがちです。
・経営者の話をじっくり聴かず、解決策を押しつける
・短期的な売上や数値改善にだけフォーカスする
これでは、経営者の本当の悩みが引き出されず、相談相手というより「単発のアドバイザー」で終わってしまいます。
私の支援スタイルではここに踏み込みます
私は「伴走型」のコンサルティングを基本としています。
経営者と同じ目線に立ち、まるで社内に参謀がひとりいるような存在として関わります。
そのために──
・社員や店長とも直接コミュニケーションを取り、人の性格や行動特性まで把握する
・経営者が抱える「人の悩み」や「教育の悩み」にも具体的に対応できる
・人事・組織づくり・教育など、経営者が本当に相談したいテーマに時間を割く
といった形で、会社全体に深く入り込みます。
また、私は「話す」よりも「聴く」ことを大切にしています。
しっかりと聴き、質問を重ねることで、経営者自身の頭の中が整理され、答えが自然に見えてくる。よくクライアントから「先生と話すと頭がスッキリします」と言われるのは、このスタイルゆえです。
つまり、私のコンサルティングは、単なる助言ではなく──
経営者が迷ったときに支えとなり、同じ方向を見て走る“伴走者”になること。
これが「人を活かす飲食店経営」を進めるうえで、最も心強い支援だと考えています。

⑦背中を押してもらえる
コンサルタントを活用すると得られること
最終的に成果を出すには、経営者も社員も「行動」するしかありません。
頭では分かっていても、日々の忙しさや目の前の業務に追われ、つい後回しになってしまう──これは多くの飲食店経営者が抱える共通の悩みです。
コンサルタントが定期的に関わることで、経営者や社員は「次までにやらなければ」という適度な緊張感を持つことができます。外部の存在がいることで行動が促され、結果として会社は前に進むのです。
他社コンサルでありがちなこと
しかし、多くのコンサルタントは「計画を立てて提案して終わり」というケースが少なくありません。
・提案はするが、行動に結びつける仕掛けがない
・宿題やタスク管理をせず、実行支援が弱い
これでは「分かったけど動けない」という状態のまま、成果に結びつかないことが多いのです。
私の支援スタイルではここに踏み込みます
私は基本的に月1回以上は必ず訪問し、現場で勉強会・ミーティング・臨店チェックなどを行います。(訪問意外に、Zoom等でも打ち合わせを行います)
その際には、単なる話し合いだけでなく「次までに必ず取り組む宿題」を出し、行動を具体的に設定します。
例えば──
・店舗の課題を抽出して整理する
・仕組みづくりのためにチェック項目をまとめる
・店長と一緒にスタッフ教育の仕組みを作り始める
こうした「未来のための行動」を必ず一歩進めてもらいます。
すると、経営者やスタッフは「先生が来るからやらなきゃ」という理由でも動き出します。最初は他力本願でも構いません。動けば必ず次につながるからです。そして行動を重ねるうちに、自発的に動けるように変化していきます。
つまり私の役割は、単なるアドバイザーではなく──
経営者と社員が“行動するきっかけ”をつくり、背中を押し続ける存在です。
これこそが、会社を確実に前進させるために必要なサポートだと考えています。

まとめ|飲食店経営コンサルタントを活用し、飲食店経営コンサルティングで「人を活かす経営」を実現する
ここまで「飲食店経営コンサルタントを活用すべき7つの理由」をご紹介してきました。一般的にコンサルを活用することで得られる効果は大きいですが、私自身が大切にしているのは、単なる「売上改善」や「仕組み導入」ではありません。
私の支援の軸は、常に 「人を活かす飲食店経営」 にあります。
私はこの「人を活かす飲食店経営」を実現するためのコンサルティング”を、現場に密着しながら実行支援しています。
理念を基盤に置き、仕組みと教育を組み合わせ、社員やスタッフが自走できるようになる。この流れをつくることで、単なる短期的な成果ではなく、会社と人が一緒に成長していける未来を実現できるのです。
相性のいい会社・経営者とは?
■相性がいい会社
・人を中心にした会社づくりを進めたい
・商品には自信があるが、マネジメントは苦手
・教育に力を入れたいと考えている
・まだアナログ文化が残っているが、変わろうとしている
■相性がいい経営者
・社員を本気で成長させたい
・勉強熱心で素直に学べる
・人の助けを借りながらも成長したい
・「人を活かす経営」を大切にしたい
逆に、売上だけに固執したり、他人任せで自分は努力しないタイプの経営者とは相性がよくありません。
私が最も嬉しい瞬間
それは、ご支援先の売上が伸びたとき以上に、スタッフが成長している姿を目の前で見られたときです。
「この会社で働いていてよかった」
「自分も成長できている」
そうスタッフが実感できることこそが、会社の持続的な成長を支える原動力だと信じています。
私はこの仕事に「命をかけている」と言っても過言ではありません。
だからこそ、ときには厳しい言葉も投げかけます。ですがそれは、経営者と社員の未来を本気で思っているからです。
最後に
もしあなたが、
「本当に会社を成長させたい」
「社員を育てたい」
「人を活かす飲食店経営を実現したい」
と強く願う経営者であれば、私は必ずお力になれるはずです。
私が全身全霊をかけて、あなたの会社の成長を伴走しながら支えていきます。
興味を持ってくださったあなたへ
さらに詳しいサポートの範囲・契約前の不安を解消したい方はこちら>>>
※当社の「人を活かす飲食店経営」の実現するためのご支援の案内は下記画像をクリック!



