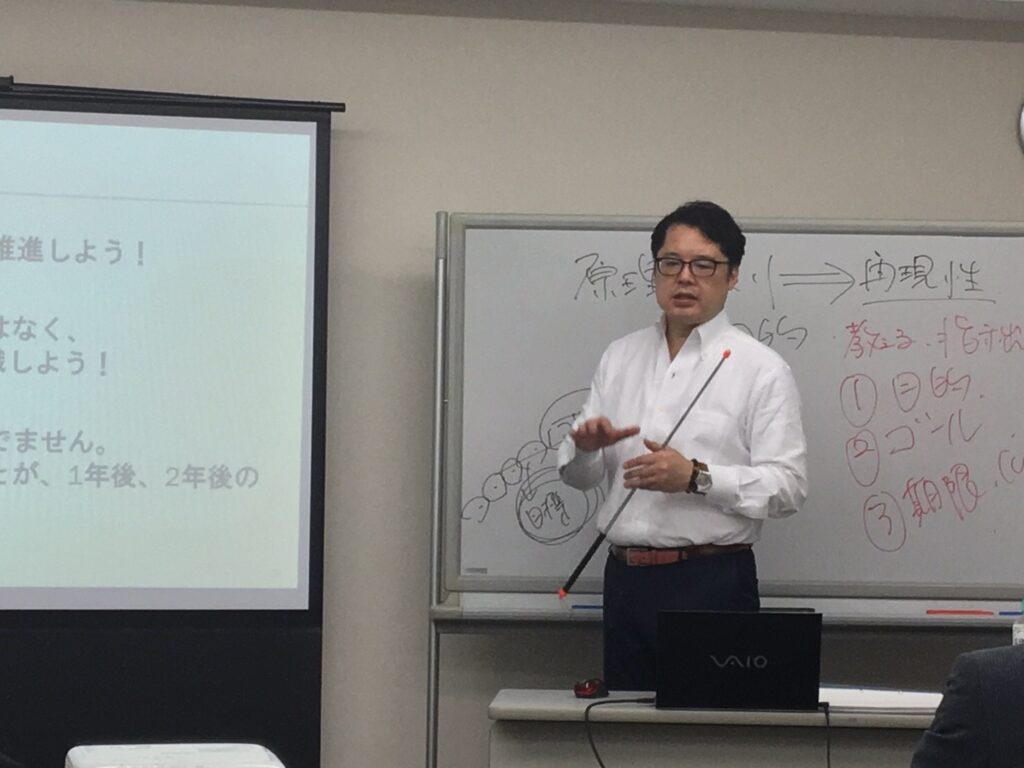
飲食店のコンサルタントを目指す人は、思っているよりも多いようですね。
私も30年近く飲食のコンサルタントをやっていますが、いい時もあれば、悪い時もあり、なかなか大変なものです(笑)
そこで、現在、あるいは、今後「飲食店コンサルタント」を目指す方に、「飲食店コンサルタント」として成功するために私自身が必要だと感じている5つの成功ポイントを挙げてみたいと思います。
1)本当の相手の要望、ニーズを把握した上で、解決することが役目

飲食店コンサルタントに限らず、「コンサルタント」の役割は、クライアント(依頼者)のニーズに対応することです。相手の「やって欲しい」ことに的確に対応できてはじめて、相手から「感謝」されます。
これはすごく当たり前なのですが、実は難しいのです。
ただ、これにこだわることが飲食店コンサルタントとしての質を高めることにもつながると私は考えています。
例えば、ご支援先(クライアント)の最初の接点でよく我々が活用するものに、「店舗診断」というものがあります。
店舗診断は客観的に店舗を見て、問題がある部分を抽出し、今後の方向性などを提案するものですが、この診断の際にも、「相手のニーズにこたえる」ことがとても大切です。必ず、相手は「ここが問題ではないか」というものを持っています。それを無視して診断書を提出しても、いくら診断内容、提案内容が優れていても契約に至らないケースもあります。
なぜなら、「この飲食店コンサルタントは、優秀かもしれないけれど、私たちの悩みをきちんと聞いてくれない」と思われてしまうからです。
やはり、コンサルタントという仕事は、クライアントの悩みや問題を解決することが最も大切な役割です。そのためにも、ご支援先(クライアント)が何を望んでいるのかを常に考え、あるいは、聴きだし、その要望に的確に応えることができるコンサルタントが優秀なコンサルタントということが言えるでしょう。
2)マーケティングの知識がないと、自分が生き残るのが難しい!

この仕事をしていて最も難しい仕事は、「仕事を採ること」、つまり飲食店さんから仕事の依頼をいただくことです。
コンサルティング自体は経験と知識を積めば、それなりにレベルは向上しますが(かなりの努力も必要であることは言うまでもありませんが・・・)、仕事を採ることは経験を積めば自然と仕事が増えるというわけではありません。
我々と同じことが言えるのは、中小企業診断士の方や社労士の方で、資格があるからといっても仕事が採れるというわけではないのです。ですから、「どうやって仕事をとるのかという戦略を、自分でしっかりと立てられること」が、独立してやっていくための最重要課題と言えます。
そのために必要な知識は何か?
それは、飲食店経営でも使える「マーケティングの知識」です。
この業界の中で、どういう立場に立って、誰に対して売っていくのかという戦略を立てることのできる知識です。このマーケティングの知識を深めることができれば、飲食店の経営アドバイスにも生かすことができます。
もちろん、最近の飲食業界の時流等も知ることが必要ですが、それよりも、「どのようにして集客するか」「どれぐらいのお金が取れるか」「契約につなげるために、どんな流れをつくるべきか」などなどの知識が増えれば間違いなく、クライアントへのアドバイスへの幅も広がります。
3)求められる経営者感覚。サラリーマンコンサルは経営者の信頼を得られない!

独立した頃、一番感じていたことは、「昔、社長がうるさく言っていたことがよく分かった」ということです。
「クライアントの売上を上げることも大切だが、うちの(会社)の売上UPのための動きも考えないと」
という苦言をたくさんいただいていました。
当時は
「それよりもクライアントの方が大事だろう?」
と反発心があったが実際にはこれは間違いです。
実は、「稼ぐ」という視点が欠如しているのです。コンサルタントは、基本的には「クライアントの売上アップ」の支援を行うことが一番の役割ですから、「稼ぐ意識」はあるだろうと思うかもしれませんが、どうしても「サラリーマンコンサルタント」の場合は、この意識は弱いのです。
なぜなら、サラリーマンコンサルタントは、たとえクライアントが契約を破棄し、売上が下がっても、自分の給与が下がるということは基本的にはありません。たとえ、上司にこっぴどく怒られても自分の「懐」が痛むことは基本的にはないのです。そのため、心構えも意識もどうしても、経営者の方からみると「甘く」見えてしまうのです。クライアントに対して「売上をアップさせましょう」と言ってもどこか「机上の空論」になってしまうのはこのセイでしょう。これが独立してからよく分かったことです。私も独立してからは、「1円」にとてもこだわるようになり、この意識がクライアントへの指導にいいように働いています。
「1円で売上をあげたい」
この考え方は、自社の売上アップにつながるというだけでなく、クライアントに対してのコンサルティングにも大きく影響するのです。
とかく、飲食店コンサルタントは、外部から「口だけだから楽でいいね」と言われることがありますが、これは「1円に対する意識の差」にあるのだと思います。そのため、この意識が弱い飲食店コンサルタントはどうしても「あるべき論」をクライアントに対して提案してしまうのです。
しかしながら、我々に依頼してくるクライアントの中には「今日の売上をどうすればいいか」という経営者の方もいらっしゃいます。にもかかわらず、その提案が「半年後に何とか赤字を解消しましょう」と言えば、どんな経営者からも契約はいただくことはないでしょう。こういった方には、「いますぐ効く特効薬を投薬するとともに、長期治療を同時に施す」ことが必要なのです。
こういった「意識をもてるかどうか」で「売れる飲食店コンサルタント」と「売れない飲食店コンサルタント」の差がでるのです。
「稼ぐ意識」が弱い人、つまり、「経営者感覚」のない人は、基本的に「飲食店コンサルタント」には向きません。経営者と同じ視点で経営の様々なアドバイスができる人をクライアントは求めているのです。
4)「チームの一員」ということをクライアントに認知させる!

コンサルティングを成功させるためには、クライアントスタッフ(特に店長さん、社員さん)の「協力」は不可欠です。いくら、飲食店コンサルタントが「いい提案」をしたとしても、実際に行動に移すのは、クライアントスタッフ。
だからこそ、クライアントスタッフから「信頼」を得ることは、コンサルティングを進めるうえでとても重要な要素だといえます。
そのためにも、クライアントスタッフに、我々飲食店コンサルタントは、「味方」であり、「チームの一員」だという意識を持ってもらえるような仕事を心がけるべきでしょう。
同じ視点で、同じ目標に向かっている「チームの一員」だというように、クライアントスタッフに思ってもらうことができれば、適切な協力が得られコンサルティングもスムーズに進めることができるでしょう。
では、どうやれば「チームの一員」という認識を持ってもらえるのでしょう?
それはごくごく単純で、私たち飲食店コンサルタントが「情熱」をもって仕事に取り組むことです。
とにかく、クライアントの目標達成のために、「真剣」に取り組んでいる姿を魅せること、これがクライアントに「信頼」を得られる一番の方法であると私は思っています。
人によっては、業務以外の「飲みにケーション」で距離を近づけて仕事を進める方がうまくいくと考えている人もいるようですが、私はかえってこういったことをする方がコンサルティングをうまく進めることができないと考えています。
その理由は、かえって「距離感」が近づきすぎて冷静な判断をすることの邪魔になると考えるからです。実際に私もクライアント先と飲むことが過去に何度もありましたが、あまりいい記憶はありません。距離感が縮めることができても、それが「いい仕事」につながるかどうかは別と考えていいでしょう。
だからこそ、ある程度適度な距離を保ちながら、とにかく真剣に、熱意をもって仕事に取り組む姿を魅せることが一番です。さらには、時にはスタッフに対して真剣に「怒る」ことも必要でしょう。この場合、注意しなければならないのは、自分の思い通りにならないから相手に対して「怒る」というのではなく、相手のために、または、そのスタッフが取った行動により周りのスタッフに迷惑をかけ、それがクライアントの目標達成の邪魔(弊害)になった場合などには、「怒る」ことが必要です。
私はいつも「うちの会社は・・・」とか「俺たちがやろうとすることの・・・」と言った会話を意識して使うようにしています。つまり、「私は君たちと同じ思いでこの仕事に取り組んでいるんだ」ということを魅せるひとつの行動と言えます。
事実、過去にコンサル終了後、「中西先生が、『俺たちの店』とか『うちの店』と言ってくれることがとてもうれしかった」という手紙をスタッフから頂いた経験があります。
やり方は個人個人変わってくるかもしれませんが、クライアントの「信頼」を得るためにも、「チームの一員である」ということ、そして、決して「腰掛的に仕事をしていない」ということを魅せるような仕事を心がけましょう!
5)飲食店の現場スタッフのことを常に考える

私は、飲食店コンサルタントは、ある程度「現場の経験があることが望ましい」と考えています。飲食の現場はちょっと特殊なところがあり、それを理解しているか、理解していないかで、提案内容の質に大きな差がでてしまいます。
また、私の強みとしては、「現場のことを熟知している」という部分にもあります。だからこそ、店舗オペレーションの改善もすべて自分で行うことができますし、また、教育についても「現場のことを知っている」からこそ、スタッフが参加しやすい内容を提案できるのです。
ただ、「現場を知らなければ飲食店コンサルタントの仕事ができないか?」と言えばそうではないと私は思います。現場を知らないからこそ、反対に経営者やスタッフが「全く違った視点」からの提案に驚かされることもあるでしょう。
しかし、「現場」を知らない方がコンサルティングをする場合、また、私のように「現場」を知っているコンサルタントでも気をつけなければならないことは、「できない提案」をしないということです。
現場が現状を変えたくないために、「できない」と言ってくるような提案ではなく、そもそも「現場」を知らないからこそ、提案してしまうと、「このコンサルは、現場のこと知らないね」と少しでもスタッフに思わせてしまうと、我々の提案はその後一切聞き入れてくれなくなります。こういう状態を作らないためにも、現場の経験がない方は、現場スタッフからのヒアリングに十二分に時間を割くようにしましょう。
朝仕事に入ってから、どんなことをして、仕込みはどんな手順でやるのか、また、賄は食べているのか、休みはどれぐらいとれているのか、休憩はあるのかないのか、などなど、とにかく店で仕事をしている状況をよく聴きだすようにしましょう。
これをしっかりとやることによって、「できない提案」をしないことにもつながりますし、現場から「言い訳」ができない提案をすることにもつながります。現場がどれだけ動けるかで、成果は大きく変わってきます。そのためにも、どんな案件であっても現場からのヒアリングには十二分に時間をかけるようにしましょう。
まとめ
飲食店のコンサルタントは、他業種のコンサルタントと違って、特殊なスキルが求められるかもしれません。特に、飲食店での現場での仕事を経験していたり、造詣が深くないと、現場スタッフからの信頼が得られず、せっかくいい提案をしても、全くクライアントの問題解決に繋がらない場合が多々あります
現場への説得力を持つための知識、経験を積んだり、また、現場スタッフの動かし方などを深めることが飲食店コンサルタントして成功するための大きな要因となるでしょう。

