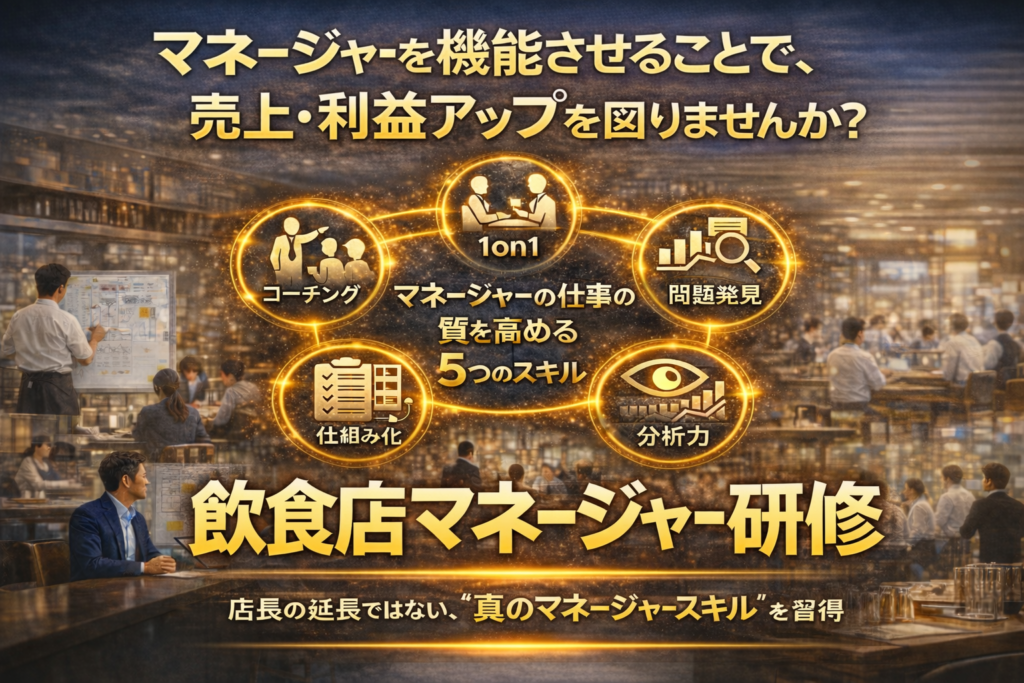マネージャーの役割の一つは「店長の育成」
マネージャーの役割は、「店舗の売上・利益向上のサポート」が一番ですが、もう一つ重要な役割があります。
それは、「店長の育成」です。
そのためにも、51日目の「マネージャーの役割を認識することがマネージャーの最初の仕事」
においてもお伝えしましたが、「自分がやる」のではなく、店長にいかにやらせるか。そして、店長が自分でできるようになるための仕組みつくりが、マネージャーの大きな仕事であるとお伝えしました。
そして、仕組みつくりと併せて重要なのが、店長にいかに「自分で考える力」を身に着けさせるかです。
仕組みも「店長に考える力」をつけさせる一つのツールですが、仕組みにはできないこともあります。そこを店長とコミュニケーションをとりながら、「考え方」を身に着けさせることも必要となるのです。
相手に考えさせるために「コーチング」を活用する
そこで、身に着けてほしいスキルが、「コーチング」なのです。
コーチングとは、「相手を最短距離でゴールに導く」というのが基本的な考え方で、コーチングを開始する際には、コーチを受ける人と目標を設定し、その目標に確実にたどり着けるよう、コーチが伴走しながら最短距離で導きます。
このコーチが伴走しながら最短距離で導くために、たくさんの「問いかけ」を相手に行い、コーチを受ける人が自分で考えたり、自分で決断して、自分で行動して、自分でゴールにたどり着くように行動します。
コーチング自体をすべて身に着けようとすると、なかなかの勉強と実習が必要ですが、すべてを身に着けるのではなく、マネージャーにはコーチングの肝である「問いかけ」のスキルを学んで活かしてほしいと思っています。
要は、この「問いかけ」のスキルが高まると、店長に答えを与えるのではなく、店長に「考えさせる」ことができるようになるからです。
原価率の改善で、コーチングを活かす方法
例えば、原価率が通常よりも2%ほど、向上している場合、ダメなマネージャーの場合だと、
「原価率がいつもより2%高くなっています。この原因は、仕入れがいつもより多くなっているからで、今月はこの後、毎日の仕入れを気を付けよう。そのためにも適正在庫に沿った発注を毎日行ってください」
と店長に、何から何まで指示してしまうのです。
これだと店長は「何も考えず・・」、すべてマネージャーの指示に従って行動してしまいますよね?
なので、結果はでる(原価率が通常に戻る)かもしれませんが、きっと、今後同じ状態になったときも、マネージャーの指示がないと対処できないのです。なぜなら、原因分析から改善まで、すべて指示されたことしかやっていないのですから・・。
これを「問いかけ」をしながら、相手に「原因から対策」まで考えさせるのです。例えば、こんな感じです。。。
マネージャー:「現状、通常月より、原価率が2%ほど高いんだけど、その原因として、どんなことが考えられるかな?考えられること、全部だしてくれる?」
店長:「そうですね。例えば、仕入れの価格が上昇したとか、ロスが増えたとか・・・・」
マネージャー:「だよね。他にはないかな?」
店長:「最近、発注を読み違えて、在庫が多くなっていることですね?」
マネージャー:「そうかもしれないね。確かに、在庫が増えると、それが原因でよりダブル発注したり、逆に、ずっと使ってないモノを捨てたりと、要は在庫が増えたことが原因で、結果、原価率が上がっているかもしれないね?」
店長:「はい。その通りだと思います。」
マネージャー:「じゃあ、どうやって、在庫を減らしていけばいいかな?」
店長:「まずは、適正在庫表があるので、それに沿って発注することを徹底します」
マネージャー:「それ以外に、気を付けることないかな?」
店長:「う~む?前に、マネージャーが言っていた、整理整頓と先入先出しですか?」
マネージャー:「そうそう。整理整頓をしておけば、発注もしやすくなるし、先入先出しが徹底すれば、古いものが使えなくなって捨てるというのもなくなると思います」
という具合に、相手に原因を考えさせ(「原因は何かな?」)、そして、その原因が原価率上昇に大きな影響を与えていることを説明したうえで、改善を”相手”に考えさせる(「どうやって、在庫を減らしていけばいいかな?)。
この「原因は何かな?」とか「なぜだと思う?」という原因を考えさせる問い、また、「どうやって・・」という対策を考えさせる問い。
このような「問い」の用語を覚え、以前にもお伝えした、「正しい仕事の進め方」に沿った形で、この「問い」を活用することで、相手自身に考えさせることができます。
これは慣れで、いつもこのような会話を繰り返し行うことで、徐々に「問いかけ」が上手になっていきます。また、「問い」のバリエーションを何個か知っておくとより、深堀りさせることができたり、より行動を具体化させることができます。
ここには、コーチングのことはこれぐらいでしか説明できませんので、興味を持った方は、ぜひ、コーチングを深めてみてください。必ず、あなたの役に立ちます。
当社のご支援内容(コンサルティングメニュー)の詳細はこちらをご覧ください>>>